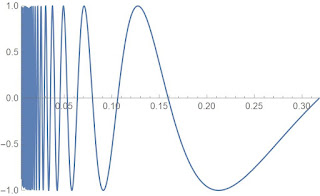[場所:オンライン(月曜日3限)]
最終回は、完備距離空間についてやりました。
完備距離空間
定義15.1
距離空間 $(X,d)$ において点列 $(x_x)$ が、$\forall \epsilon>0$ に対して、
$\exists N\in {\mathbb N}$ と、$\forall m,n>N$ に対して、$d(x_n,x_m)<\epsilon$
を満たすとき、$(x_n)$ をコーシー列という。
この定義は ${\mathbb R}$ 上のコーシー列の一般化になっています。
一般に、コーシー列は収束列とは限りません。
たとえば、$a_n=1/n$ とすると、$(0,1)$ において、$a_n$ は
コーシー列ですが、$(0,1)$ に収束先はありません。
つぎに、距離空間の完備性の定義をします。
定義15.2
$(X,d)$ を距離空間とする。任意のコーシー列が収束するとき、
$(X,d)$ は完備という。
先ほどの例 $(0,1)$ は完備距離空間ではないということになります。
完備距離空間の例は以下のものがあります。
定義15.1 ${\mathbb R}$ は完備距離空間である。
定理15.2 コーシー列 $(a_n)$ は有界である。
(証明) $\forall \epsilon>0$ に対して、
$\exists N\in {\mathbb N}$ において、$n_0,m>N$ となる自然数で
$n_0$ を固定しておきます。
このとき、$d(a_{n_0},a_m)<\epsilon$ です。
$\{d(a_{n_0},a_{n})|n\le N\}$ は高々有限集合なので、その最大が存在して、
それを $\delta$ とします。よって、
$d(a_{n_0},a_n)<\max\{\delta,\epsilon\}$となります。
$n,m\in {\mathbb N}$ に対して、
$d(a_n,a_m)\le d(a_n,a_{n_0})+d(a_{n_0},a_m)\le 2\max\{\delta,\epsilon\}$
$\text{diam}(\{a_n|a\in {\mathbb N}\})\le 2\max\{\delta,\epsilon\}$
よってコーシー列 $(a_n)$ は有界となります。$\Box$
次の定義をしておきます。
定義15.3
$(a_n)$ を 位相空間 $X$ の点列 $(a_n)$に対して、
$${\mathbb N}\ni k\mapsto n_k\in {\mathbb N}$$
を単射とする。
このとき、$(a_{n_k})$ を $(a_n)$ の部分列という。
定理15.3(ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理)
${\mathbb R}$ の任意の有界数列は収束する部分列をもつ。
(証明) $(x_n)$ を${\mathbb R}$ の有界数列とします。
このとき、$\{x_n|x\in {\mathbb N}\}\subset [-M,M]$ とします。
拡大縮小、平行移動をして $\{x_n|n\in{\mathbb N}\}\subset [0,1]$ としておきます。
定理13.8 (こちらのページ)と同様に、区間を半分にしていくことで、
$$[0,1]\supset[a_1,b_1]\supset [a_2,b_2]\supset \cdots $$
各 $n\in{\mathbb N}$ に対して、$[a_n,b_n]$ において、
点列 $(x_n)$ が無限個入るようにしておきます。
このとき、$x_{n_1}\in [a_1,b_1]$ とし、$n_1<n_2$
かつ $x_{n_2}\in [a_2,b_2]$ となるようにします。
同様に、$n_{k-1}<n_{k}$ であって、$x_{n_k}\in [a_k,b_k]$ を満たすように
します。
そうすると、上の区間の減少列において、
$a_n,b_n\to x$ が成り立ち、$\{x\}=\cap_{n=1}^\infty [a_n,b_n]$ となります。
$(x_n)$ の部分列 $(x_{n_k})$ であって $a_k\le x_{n_k}\le b_k$ を満たします。
また、$a_k,b_k\to x$ を満たすので、$x_{n_k}\to x$ となります。
よって、$(x_n)$ の部分列 $(x_{n_k})$ は $x$ に収束する部分列になります。$\Box$
また、次の定理が成り立ちます。
定理15.4
コーシー列 $(a_n)$ が収束する部分列をもつなら、$(a_n)$ は収束列である。
この証明は $\epsilon$-$N$ 論法を使って簡単に証明できるので、ここでは省略します。
この定理を用いることで、上の$ {\mathbb R}$ は完備距離空間であることがわかります。
(定理15.1の証明)
$(a_n)$ を任意の ${\mathbb R}$ のコーシー列とします。
このとき、$(a_n)$ は有界数列なので、ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの
定理により、収束する部分列を持ちます。
$(a_n)$ が収束する部分列をもつので、定理15.4から$(a_n)$ は収束列ということに
なります。よって、${\mathbb R}$ は完備距離空間になりました。$\Box$
ここで以下を示しましょう。
定理15.5
距離空間において以下が同値である。
・コンパクト空間
・全有界かつ完備
まず、上から下の条件を導きましょう。
定理15.6
コンパクト距離空間は全有界かつ完備である。
(証明) コンパクト距離空間は全有界であることは既に示したので、
完備性を示そう。
$(a_n)$ を任意のコーシー列とします。
$A=\{a_n|n\in {\mathbb N}\}$
とします。
$A$ が集積点を持たないとします。
このとき、$B_d(x,\epsilon_x)\cap A=\emptyset $ または $\{x\}$
であり、$\{B_d(x,\epsilon_x)|x\in X\}$ は $X$ の開被覆であり、
コンパクト性から、$\{B_d(x_i,\epsilon_{x_i})|i=1,\cdots, n\}$ が
部分開被覆となります。
よって、$A=\cup_{i=1,\cdots,n}(B_d(x_i,\epsilon_{x_i}\cap A)\subset \{x_i|i=1,\cdots,n\}$
より、$A$ は有限集合になります。
そうすると、ある $p\in A$ に対して、無限個の $(a_n)$ が存在して、
$a_n=p$ となります。
よって、収束する部分列を持ちます。
一方、
$A$ に集積点を持つとします。
それを $x\in X$ とします。
このとき、$a_{n_1}\in B_d(x,1)\cap (A\setminus \{x\})$
とします。このとき、$\delta_1=d(a_{n_1},x)/2$ とします。
条件から $\delta_1<\frac{1}{2}$ です。
$a_{n_2}\in B_d(x,\delta_1)\cap (A\setminus\{x\})$
として、$\delta_2=\frac{d(a_{n_2},x)}{2}$ とすると、
$\delta_2<\frac{\delta_1}{2}<\frac{1}{4}$
$a_{n_3}\in B_d(x,\delta_2)\cap(A\setminus \{x\})$
より、これを続けることで、$\delta_n<\frac{1}{2^n}$ です。
また、選び方から、$a_{n_1},a_{n_2}, a_{n_3},\cdots$ は全て違う点であるから、
$a_{n_k}$ は部分列であることがわかります。
また、$d(a_{n_k},x)<\delta_k<\frac{1}{2^k}$ であるから、
$a_{n_k}\to x$ であることが分かります。
どちらにしても、コーシー列 $(a_n)$ に対して 収束する部分列 $(a_{n_k})$
が存在します。
よって、定理15.4から、$(a_n)$ は収束する列になります。
よって、$(X,d)$ は完備になります。$\Box$
次に上の逆を示しましょう。その前に次を示しておきます。
定理15.7 全有界な距離空間は、任意の点列は、コーシー列となる部分列をもつ。
(証明) $(X,d)$ を全有界な距離空間とします。
今、$\forall n\in {\mathbb N}$ に対して、
有限点 $\{x_1^n,\cdots, x_{m_n}^n\}$ が存在して、
$$X=\cup_{k=1}^{m_n}B_d\left(x^n_k,\frac{1}{n}\right)$$
が成り立ちます。
ここで、$(a_n)$ を任意の点列とします。
$B_1=B_d(x_{k_1}^1,1)$
$B_2=B_d(x_{k_1}^1,1)\cap B_d(x_{k_2}^2,\frac{1}{2})$
$B_3=B_d(x_{k_1}^1,1)\cap B_d(x_{k_2}^2,\frac{1}{2})\cap B_d(x_{k_3}^3,\frac{1}{3})$
$\cdots$
のようにして、$B_i$ には、$(a_n)$ のうち無限個の点列を含むようにすることが
できます。同じことですが、そのような $k_i$ を選ぶことができます。
そうすると、
$$B_1\supset B_2\supset B_3\cdots$$
となることがわかります。
こうすることで、$a_{n_1}\in B_1, a_{n_2}\in B_2,\cdots$
のように点列を選ぶことができて、$n_1<n_2<\cdots$ と仮定することができます。
よって、部分列 $a_{n_k}$ をとることができます。
今、$\epsilon>0$ に対して、$\frac{1}{2N}<\epsilon$ となる自然数 $N$ が存在して、
$\forall k,l>N$ に対して、
$d(a_{n_k},a_{n_l})\le d(a_{n_k},x^N_{n_k})+d(x^N_{n_k},a_{n_l})<\frac{1}{N}+\frac{1}{N}<\epsilon$
を満たします。
よって、$a_{n_k}$ はコーシー列となります。$\Box$
では、先ほどの定理15.5の下から上を示しましょう。
定理15.8
全有界かつ完備距離空間はコンパクト空間である。
(証明) $(X,d)$ が全有界完備であるとします。
このとき、$(X,\mathcal{O}_{d})$ は全有界かつ完備であるから、
$X$ はリンデレフ空間になります。
よって、任意の開被覆 $\mathcal{U}\subset \mathcal{O}_d$ に対して、
高々可算部分被覆 $\mathcal{V}\subset \mathcal{U}$ が
存在します。$\mathcal{V}$ が有限であれば、証明が終わるので、
可算(無限)集合であるとします。
$\mathcal{V}$ にどんな有限部分集合も $X$ を被覆しないと仮定しておきます。
どんな $n\in {\mathbb N}$ に対しても、
$x_n\not\in V_1\cup \cdots \cup V_n$ をとり、点列 $(x_n)$ を構成します。
$\forall i\in {\mathbb N}$ に対しても $V_i$ には高々有限個の $x_n$ のみしか
含みません。
この点列 $(x_n)$ には定理15.7 から部分コーシー列 $(x_{n_k})$ が存在します。
よって、完備性から $(x_{n_k})$ は収束し、その収束先を $x$ とおくと、
$x\in V_n$ に対して、$V_n$ は $x$ の近傍であるから、$V_n$ に含まれる
無限個の $x_{n_k}$ が存在することになります。
これは、$V_n$ には高々有限個の $x_{n_k}$ しか存在しないことに矛盾します。
よって、$\mathcal{V}$ は、有限部分被覆が存在します。
これは $\mathcal{U}$ の有限部分被覆でもあるから、
$X$ はコンパクトであることになります。$\Box$
これにより、定理15.5のコンパクト距離空間が全有界かつ完備であること
と同値であることが証明できました。
ベールの定理
ここで、完備距離空間の性質としてベールの定理を示しておきます。
そのために以下の定義をしておきます。
定義15.4
位相空間 $(X,d)$ に対して、$A\subset X$ が
$\text{Int}(\text{Cl}(A))=\emptyset$ であるとき、$A$ は疎集合であるという。
また、疎集合の可算個の和集合のことを第1類という。
また、第1類ではない集合を第2類という。
疎集合であることは、上と同値な条件に、
$\text{Cl}(\text{Int}(A^c))=X$ があります。
これは、以前示した、
$(\text{Int}(B))^c=\text{Cl}(B^c)$
$(\text{Cl}(B))^c=\text{Int}(B^c)$
により導けます。
また、条件から、疎集合の部分集合は全て疎集合であることが分かります。
注意すべきことは、疎集合というのは、入っている位相空間に依存しますし、
どのように入っているかにも依存します。
たとえば、$[0,1]\subset {\mathbb R}$ は疎集合ではありませんが、
$[0,1]\subset [0,1]\times [0,1]$ は疎集合となります。
特に、疎集合かどうかは位相的性質ではありません。
例15.2
疎集合の例としては、$({\mathbb R},\mathcal{O}_{d_1})$ 上の
有限点集合は疎集合です。
よって、${\mathbb R}$ 上の可算集合は全て第1類ということになります。
例えば有理数全体の集合 ${\mathbb Q}\subset {\mathbb R}$
は通常のユークリッド距離位相空間において第1類となります。
ただ、疎集合ではありません。
ここで、疎集合を特徴づけましょう。
命題15.1
稠密開集合の補集合は疎集合である。
(証明) $D$ を稠密開集合であるとします。
条件から、
$\text{Int}(D)=D$ かつ $\text{Cl}(D)=X$ であるから、
$\text{Int}(\text{Cl}(D^c))=\text{Int}((\text{Int}(D))^c)=\text{Int}(D^c)=(\text{Cl}(D))^c=X^c=\emptyset$
となります。
よって、$D^c$ が疎集合ということになります。$\Box$
次の命題を示しましょう。
命題15.2
$(X,\mathcal{O})$ を位相空間とするとき、以下は同値。
・$A\subset X$ が疎集合である
・稠密開集合 $D$ が存在して、$A\subset D^c$ となる。
(証明) $(\Rightarrow)$ を示します。
$A\subset X$ を疎集合とします。
このとき、$D=(A^c)^\circ$ とおくと、$D$ は開集合であり、
$\text{Cl}(D)=\overline{(A^c)^\circ}=X$ となります。
よって、$D$ は稠密開集合となります。
また、$D\subset A^c$ であるので条件を満たします。
($\Leftarrow$) を示します。
$D$ を稠密開集合とし、$A\subset D^c$ とします。
このとき、命題15.1から、$D^c$ は疎集合であり、
疎集合の部分集合は疎集合であるから
$A$ が疎集合であることになります。$\Box$
ここで、ベールの定理を書いておきます。
定理15.9(ベールの定理)
$(X,d)$ を完備距離空間とする。
$D_i$ が可算個の稠密開集合のとき、
$\cap_{i=1}^\infty D_i$ は $X$ で稠密集合になる。
この証明を考える前に、いくつか説明をしておきます。
まずこの定理が補集合では何を言っているか考えましょう。
するとこうなります。
完備距離空間において、
$A_i$ を可算個の稠密開集合の補集合とする。
このとき、
$A=\cup_{i=1}^\infty A_i$ は、$A^\circ=\emptyset$ である。
また、その部分集合を取ると、
完備距離空間において、
$A_i$ を可算個の疎集合とする。
このとき、
$A=\cup_{i=1}^\infty A_i$ は、$A^\circ=\emptyset$ である。
つまり、ベールの定理は、
完備距離空間において、
$A\subset X$ が第1類ならば、 $A^\circ =\emptyset$ となる。
さらに、対偶を取れば、
$A$ が内点を持つとすると、$A$ は可算個の疎集合の和集合で書けない。
つまり、第2類集合である。
特に、$X$ が完備距離空間であれば、
$A=X$ は可算個の疎集合の和によって書くことができない。
評語的に言えば、
「チリ(疎集合)もつもれど(可算和集合をとっても)山(内点を持つ集合)にならない」
ということが言えます。
例15.3 例えば、${\mathbb R}^2$ は完備距離空間ですが、
可算個の直線によって覆うことができない。
また、
例15.4 有理数空間は、完備距離空間に同相ではない。
なぜなら、もし同相なら、1点集合は、疎集合であるから、${\mathbb Q}$
は、疎集合の可算和集合になってしまうからです。
また、一般化して、孤立点を含まなければ完備距離空間は非可算個の点を含みます。
もちろん、離散距離空間は、可算個でも完備距離空間になります。
ではここで、ベールの定理の証明をしておきます。
(証明) $(X,d)$ を完備距離空間とします。
$D_i$ を稠密開集合とします。($i=1,2,\cdots$)
この時、$\cap_{i=1}^nD_i$ が $X$ において稠密であることを示します。
$\forall x\in X$ として、$\forall \epsilon>0$ に対して、
$\epsilon_0=\epsilon$ とし、$x_0=x$ とおきます。
このとき、
$B_d(x_0,\epsilon)\cap D_i\neq \emptyset$
であるから、$x_1\in B_d(x_0,\epsilon_0)\cap D_i$ を取ります。
また、
$0<\epsilon_1<\frac{1}{2}$ かつ、
$$\text{Cl}(B_d(x_1,\epsilon_1))\subset B_d(x_0,\epsilon_0)\cap D_1$$
とすることができます。
それは、$B_d(x,\epsilon)$ かつ $D_i$ がどちらも開集合であり、
距離空間が正則空間であることからわかります。
また、$B_d(x_1,\epsilon_1)\cap D_2\neq \emptyset$ であることから、
$x_2\in B_d(x_1,\epsilon_1)\cap D_2$ を取り、
$0<\epsilon_2<\frac{1}{4}$ を取り、
$$\text{Cl}(B_d(x_2,\epsilon_2))\subset B_d(x_1,\epsilon_1)\cap D_2$$
とすることができます。このようにして、
任意の $n\in {\mathbb N}$ に対して、
$$\text{Cl}(B_d(x_n,\epsilon_n))\subset B_d(x_{n-1},\epsilon_{n-1})\cap D_n$$
かつ $0<\epsilon_n<\frac{1}{2^n}$ を取ることができます。
よって、
$\forall m>n\in {\mathbb N}$ に対して、
$B_d(x_m,\epsilon_m)\subset B_d(x_{m-1},\epsilon_{m-1})\subset \cdots\subset B_d(x_n,\epsilon_n)$
となります。
このことから、$d(x_m,x_n)<\epsilon_n<\frac{1}{2^n}$ より、
$(x_n)$ はコーシー列であり、
完備性から、ある $x_\infty$ に収束します。
また、$\forall n\in {\mathbb N}$ に対して $\forall m>n$ に対して、
$x_m\in B_d(x_n,\epsilon_n)$ であるから、
$x_\infty\in \text{Cl}(B_d(x_n,\epsilon_n))$ となります。
よって $x_\infty\in D_n$ かつ、$B_d(x_n,\epsilon)$ であることがわかります。
特に、$x_\infty\in B_d(x,\epsilon)$ であるから、$x_\infty\in B_d(x,\epsilon)\cap_{n=1}^\infty D_n$
であり、
$x_\infty\in \overline{\cap_{n=1}^\infty D_n}$ であることがわかります。
よって、$\cap_{n=1}^\infty D_n$ は $X$ で稠密であることがわかります。 $\Box$
完備化
最後に、完備化の話をして終わります。
完備化の定義をしておきます。
$(X,d)$ を距離空間とします。
このとき、ある完備距離空間 $(\hat{X},\hat{d})$ が存在して、
$h(X)\subset \hat{X}$ が稠密となる単射連続写像 $h:X\to \hat{X}$ が存在するとき、
$(\hat{X},h)$ を $X$ の完備化と言います。
例えば、以下の例ががあります。
例15.6
$({\mathbb R},d_1)$ における $({\mathbb Q},d_1)$ の通常の埋め込みは完備化である。
また、次の例を考えます。
$C^\ast(X)$ を $X$ 上の有界な実数値連続関数全体とします。
$f,g\in C^\ast(X)$ に対して、
$$d_{\sup}^X(f,g)=\sup\{|f(x)-g(x)||x\in X\}$$
と定義すると、$(C^\ast(X),d_{\sup}^X)$ は完備距離空間となります。
完備化についての定理を与えて証明することで終わります。
定理15.10
$(X,d)$ を距離空間とする。
このとき、$X$ の完備化 $(\hat{X},h)$ が存在し、
完備化は等長写像を除いて一意的である。
(証明) $(X,d)$ を距離空間とします。
$a,x\in X$ に対して、
$\varphi_x(z)=d(a,z)-d(x,z)$
とすることで、$\varphi_z\in C^\ast(X)$ が構成します。
ここで、$\Phi(x)=\varphi_x$ とします。
$\Phi$ が単射であることを示しておきます。
$\Phi(x)=\Phi(y)$ であるとします。
このとき、任意の $z\in X$ に対して、$d(x,z)=d(y,z)$ であり、
特に $z=x$ とおくことで、$0=d(x,y)$ であるから、$x=y$ となります。
よって、単射
$$\Phi:X\to C^\ast(X)$$
を得ます。
このとき、$|\varphi_x(z)-\varphi_y(z)|=|d(a,z)-d(x,z)-(d(a,z)-d(y,z))|=|d(x,z)-d(y,z)|\le d(x,y)$
より、
$d_\sup^X(\varphi_x,\varphi_y)\le d(x,y)$
が成り立ちます。この不等式から $\Phi$ が連続であることがわかり、同様に、$d(x,y)\le d_\sup^X(\varphi_x,\varphi_y)$
も成り立つことがわかります。
$\Phi:X\to C^\ast(X)$ は距離を保つ連続写像であることがわかります
$\hat{X}=\text{Cl}(\Phi(X))\subset C^\ast(X)$ とすることで、
$\hat{X}$ は完備距離空間であり、$X\subset \hat{X}$
は完備化となります。
一意性に対してはここでは省略します。$\Box$
ここで使ったのは、完備距離空間の中の閉集合はまた完備距離空間であることでした。